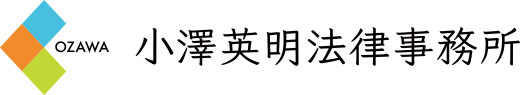住民参加のまちづくり
2025年7月11日
鷺 坂 長 美
標題は少々大げさですが、公共事業の設計等に地域住民をどのように巻き込んでいくか、ということです。今から20年程前のお話で、岡山県庁で企画部長をしていた時のことです。
当時の公共事業と言えば、道路とか河川の土木事業が中心で、河川改修等においては洪水対策として、百年に一回の豪雨、人の一生のうちにあるかないかの豪雨に耐えられるような堤防を作ることが主な事業でした。河川を取り巻く景観や日々の暮らしの中の河川ということはあまり考えていなかったのでは、と思われます。したがって、工事完了後、周辺住民からの評判は芳しくないことが多く、不平不満の対象になることもしばしばでした。極端な例でいえば、河川改修によって、いわば憩いの場であった河川が、三面をコンクリート護岸で固められ、立入禁止とされてしまった、というようなことです。
当時から公共事業については事業費1%を上乗せして、地域の景観にマッチさせる、とか文化的な価値を付加する、という議論がありました。工事の実施設計以前の基本設計段階において、洪水対策という観点以外の付加価値を加味していこうという試みです。岡山県高梁川河川改修事業の一工区について、土木部ではなく企画部主導で実験的に行ったことがあります。まず、工事の基本設計段階で地域住民の方々に集まってもらい、ここの護岸はどういう形にするのか、河川の流量が少ないときの河川敷の利用をどうするのか、など、さまざまな意見がだされました。住民の間で意見がまとまらない場合には多数決をすることもあります。大変手間のかかる作業で、実験的な試みでしたので、継続的な予算の確保はできませんでしたが、何年か後、その事業について、地域の人からも評判がよかったと聞いて安堵したものです。
その後、河川改修の在り方もいろいろ議論があり、1997年、私が岡山県での勤務を終え、旧自治省へ戻ったときに河川法の改正が行われました。「河川環境の整備と保全」も河川法の目的の一つとされ、親水護岸等いわゆる「親水」という言葉が河川改修事業にも取り入れられていったと思います。
私自身は2001年に環境省へ移りましたが、当時の環境省では、学校のエコ改修事業を手掛けていました。コンセプトとしては、老朽化した学校の校舎を建て替えるのではなく、リサイクルではありませんが、使える所は使って改修していこうというものです。島根県隠岐郡海士町の中学校の改修事業がモデル事業として採択されていました。海士町では生徒数も激減していたため、老朽校舎対策として、学校をどうするか、という議論もされていたそうです。そこで、1年ぐらいかけて、学校の在り方も含め改修方法等を住民を交えて議論し、基本設計につなげていきました。生徒数が激減していますので、教室は余ります。教室を統合して図書室機能を持った多目的ルームにしたらどうか、とか、給食の調理場からの動線はこうしたらいいのではないか、などいろいろな意見がだされたそうです。もちろんエコ改修ですので、断熱、遮熱等の省エネ技術の活用や壁面緑化等も話題となります。住民も関与した学校改修ですので、愛着も沸きます。生徒数は多くありませんでしたが、できる限りそこに通わせようとなったと言います。
当時の海士町は町長さんの個性的なリーダーシップにより、「地域づくり」でも全国的に有名でした。地元に観光産業をはじめ車エビの養殖、畜産事業等を進め、住宅手当として一定期間の所得補償等をして、全国からいわゆる「Iターン」(「Uターン」でも「Jターン」でもなく、地元とは関係のない土地に転居すること)人材を集めていました。海士中学校のエコ改修を見学に行ったときです。海士町の観光協会に立ち寄る機会がありました。そこでは日本語の流暢な外国人の方が働いていました。私の若いころの赴任地である大分県にある立命館アジア太平洋大学に留学して、そのまま日本で就職活動し、海士町観光協会に就職した、ということを聞いたときは不思議なご縁を感じたものです。