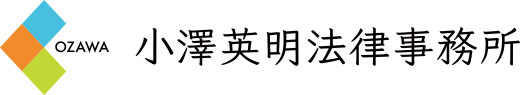都市プランナーの雑読記 その94
大澤真幸・平野啓一郎『理想の国へ 歴史の転換期をめぐって』中公新書ラクレ、2022.07
2025年3月28日
大 村 謙二郎
社会学者である大澤真幸のエッセイ、論説は比較的読んでいる方だが、平野啓一郎のエッセイはいくつか読んだが、小説は読んだことがない。ただ、ネット上での発言などを通じて、リベラルな考えの持ち主であること、物事を原理的に徹底的に考える人であり、小説家の枠を超えた、哲学者の面も持っている人かなと感じていた。学生で芥川賞を受賞するなど文学的才能もあふれる人なのだろう。
この二人は以前から顔見知りで何度か、対談をしてきたとの事だ。
本書の元になった対談は平成の天皇が退位宣言をした後の2019年1月、コロナ禍中の2020年8月、2021年3月、さらにロシアのウクライナ侵攻が続く2022年4月の、計4回だ。この対談を基に改稿したのが本書である。アクチュアルで時々刻々と事態が進行する中で鋭い議論が交わされている。
第1章は「人類史レヴェルの移行期の中で」と題して日本の問題を巨視的に議論している。人類史の長い歴史で見ると日本人というアイデンティティは、ほんの最近出来たものであり、それほど根がしっかりしたものでないことを二人は確認しており、同感だ。
第2章は「平成を経て日本はどう変化したか」と題して議論を展開している。明治以降、西暦と元号を併用するシステムを日本が採用してきたが、昭和も50年代以降、さらに平成になって、平成という元号で何かを意識することが難しくなってきた所以を議論している。少なくとも昭和30年代頃までは10年きざみで、ある出来事であったとイメージできたのは日本国内が閉じており、日本国内のことを中心に世の中の動きを理解できていたのだが、1970年代以降、国際化、海外との様々な形でのつながりが強まり、グローバル化の進展、情報の伝搬速度の飛躍的増大の中で日本を閉じて意識することが困難になってきたことが大きな要因でないかと大澤、平野は指摘しており、納得できる説明だ。
平成は何とものっぺりして空虚な時代であり、平成の怪物などと行った言葉が出てきてもそれで、何か、平成をイメージできない時代になってきている。果たして令和がどうなるのか。私のような昭和の記憶をある程度、世代的に共有していると考えている世代にとって、平成世代意識、令和世代意識というものが芽生えるものなのか大いに疑問だ。
第3章は「世界から取り残される日本 あの三島がその三島になった日」と題して、1970年11月25日に市ヶ谷の自衛隊駐屯地で自決した三島をテーマに日本が世界から取り残される事態について議論を交わしている。
三島が自決する前の1970年7月に「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜け目がない、或る経済大国が極東の一角に残るであろう。」と産経新聞の夕刊に書いていた。
からっぽな、世界から取り残される日本について、三島の文学、思想に詳しい二人が語り合っている。日本的とは何かが真摯に議論されている。
第4章は「破局を免れるために 環境・コモン・格差」について、斎藤幸平の『人新世の「資本論」』を導入に、地球環境問題、資本主義を乗り越えるもの、コモンのあり方について議論を行っている。
大澤は資本主義の克服を可能性として論じているが、平野はコモンについても資本主義の廃棄についてもいささか懐疑的である。もちろん両者で対立しているわけでないが、私もコモンをどう統治していくのか、国民国家という枠組みをそう簡単に廃棄できないと考えるので、この章の議論はなかなか、すっきり同感は出来なかった。
第5章は「国を愛する」ということ、と題して、ロシアのウクライナ侵攻を巡って議論を交わしている。愛国の意味は何か。手段としての正義と目的としての正義を分けて考えること、相手を一方的に断罪して終わるような形での戦争の終結は不可能な場合、どういった着地点を探せるのか。興味深いし、深い議論が展開されている。
通読して、すっきりした解を得られるわけでないが、物事をいろいろ多面的に見ること、常識を疑うことの大事さをあらためて感じた。