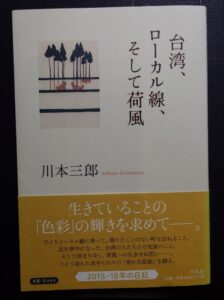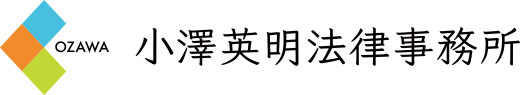都市プランナーの雑読記 その93
川本三郎『台湾、ローカル線、そして荷風』平凡社、2019.03
2025年3月13日
大 村 謙二郎
腰帯に2015年-2018年の日記との表記があるように、川本が雑誌「東京人」の2015年8月号から2018年7月号まで、「川本三郎 東京つれづれ日誌」のタイトルで連載したエッセイをとりまとめたものが本書だ。川本は好きな作家、エッセイストのひとりで、彼の著作は比較的読んできた。ほぼ同世代の作家だ。東大都市工で同期だったN君の麻布学園時代の同級生でもある。
2008年に愛妻を亡くし、独居老人となったと自称している。
70代になって、彼の著作が台湾で翻訳出版された縁から、台湾とのつきあいが始まり、台湾にも度々訪れるようになったとのことだ。
この2月初旬、台北、台南を訪れた。台北では大稲埕というエリアも訪れた。清代末期から日本統治時代にかけて水運で栄えた貿易の街であり、そのメインストリートの迪化街にはレンガ造りのバロック風の街並みが連なっており、乾物、漢方薬の問屋街、お菓子などを扱っている土産店が数多く立地しており多くの観光客が訪れる人気のスポットとなっている。その一角に郭治美書店という、地元でも評判の書店がある。現地のプランナーの人に案内されてここに入ったが、その一角に日本人の作家のコーナーがあり、川本三郎の著作で翻訳されたものが数点並んでいた。川本のエッセイが台湾の人にも愛読されているのだと感心した。
台湾の人々は総じて、親日的なようで、台湾の最近の都市再開発は日本統治時代の歴史的な建物、文化ストックを再生、活用することがトレンドとなっているようだ。Adaptive Reuse適合的再生利用という、言葉があるそうだが、日本のこれからの再開発でもこういった動きが出てくると思われる。
川本は自由な時間を持てる職業という利点を活かし、各地を旅し、音楽会、美術展、文芸展などを訪れ、また、彼の趣味でもある、ローカル線での旅行での出来事などを書いている。特にまとまった主張があるわけでない。
彼は権威主義的な物言いや新しい、大きな建物に対して批判的である。個人的には市井の人々の生活が感じられる風景、町の平凡な食堂、居酒屋でのビールとつまみ、ラーメンを好んでいる。彼が多感な少年時代に育った昭和、とりわけ30年代のすがれた風景に愛着を持っているようだ。
それにしても、この人の守備範囲は広くて、知らない文学者、作家、画家、音楽家のこと、映画のことなどが、嫌味でなくさりげなく書かれており、その博覧強記ぶりに驚かされる。到底真似できないが、こういった老年になり、ある種の寂しさを持ちながらも「豊かな孤独」を楽しむ姿勢にひかれるところが多い。