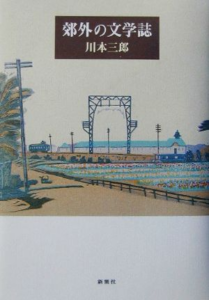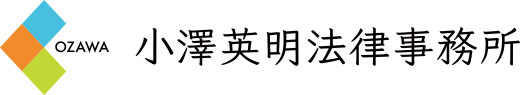都市プランナーの雑読記 その101
川本三郎『郊外の文学誌』新潮社、2003.02
2025年8月12日
大 村 謙二郎
ずいぶん前に買ったのだが、放置してあった本だ。最近、川本の「台湾、ローカル線、そして荷風」を読み終え、この人のエッセイを続けて読みたくなって、週末に1章ごとを読み続けるスタイルで時間をかけて読んだ。
昨年、お亡くなりになった渡辺俊一さんには都市計画研究、都市計画史研究について多くの教えを受け、学恩を負っている。その渡辺俊一さんとは建築研究所でながいあいだご一緒した。その渡辺俊一さんが建築研究所の第6部長に就任し、いろいろ新機軸を打ち出された。その中で、建研アーバンフォーラムという形で都市計画、都市論に関連する専門家、話題の人を呼んで話を聞く、官民連携の研究会を開催していた。
その何回目だったか忘れたが川本三郎を呼んで話を聞く会を持った。当時彼は都市論に関連するエッセイを著作の形で次々と刊行していて、大変興味深く読んでいたので、川本さんの私的都市論の講演は大変面白かった。反権力ではないが、権力に阿ることを嫌い、また、バブル下で進められていた、東京の巨大都市開発に違和感を示し、低層の街並み、昔からの自営業者で構成される商店街などに共感を示していた姿勢に同感の思いを持った。川本には昭和30年代のまだ戦前の良き東京の面影が残る風景、情景が好ましいものであり、永井荷風にひかれるのも、彼の幼年、少年時代の原体験、原風景につながるモノを感じるからだろう。
さて、本書は、代々木で生まれ、戦後、中央性沿線の街、阿佐ヶ谷で育った、ある意味で、東京西郊の典型的郊外住宅地で育った川本が、明治末から急速に都市郊外化が進んだ東京の郊外住宅地について、中産階級の暮らしの場として、文学作品はどう扱ってきたのか、また文学作品を種に郊外住宅地を跡づける試みの文学批評、郊外まち歩きエッセイの趣を持った作品だ。
序の部分の「なぜ郊外か」は本書刊行にあたっての書き下ろしだが、その他の章は文芸誌「新潮」に平成12年1月号から12月号にわたって、一年間に連載したものに加筆したものである。
取り上げている作家、文学作品も多彩であり、現在では郊外とはいえない土地も明治末、昭和初期にはまだ郊外の面影が多分に残っていた場所が取り上げられている。東京の西郊外部分が多いがそれでも、葛飾界隈、蒲田とその周辺が取り上げられ、それに触れた小説、エッセイ、映画作品が取り上げられている。また、それぞれの地域、場所の地誌、専門家の論説等も適切に引用され、東京の郊外地を歴史的に回顧し、懐かしい風景を描き出している。
終章に取り上げられている庄野潤三(「郊外に憩いあり」)については読んだことのない知らない作家だったが、小市民的な幸せ、さりげない日常、家族との関係を連作の形で書いてきた人との紹介があり、従来の私小説文学者が描く、苦悩に満ちた生活、苦労とは隔絶した郊外の生活像を描いた庄野潤三の先駆的業績を評価しており、興味深く読めた。
東京の郊外を懐かしみ、これからの都市郊外のあり方を考えさせてくれる本だ。味わい深い。