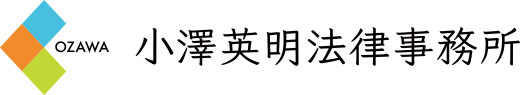楼蘭花 (2025年3月)
2025年3月18日
小 澤 英 明
2月下旬、庭に楼蘭花(ろうらんか)が咲いた。切って玄関の花瓶に挿した(写真参照)。椿の本を見て、欲しいと思っていた種類の椿だが、数年前に武蔵境の船木園で苗を購入できた。船木園は、東京の椿園では一番充実しているように思う。かなりの種類の苗が秋口から揃う。カタログを見てネットの写真で好きな色形の種類を選べば、通信販売で買えるが、武蔵境まで私の練馬の自宅からそれほど遠くもないので、車で出かけて購入できる。この楼蘭花は、もう庭に椿を植えるところがほとんどないという頃に買ったので、家の裏口通路という気の毒な場所に植えられてしまった。しかし、その通路は家の駐車場から玄関までの通路でもあり、毎日のように通るため、鑑賞者は私と妻の二人だけでしかないが、花の咲くのを見逃すことはない。
この楼蘭花のような咲き方は唐子咲きと呼ばれている。唐子人形の髪を結ったかたちに花のおしべが集まって盛り上がって咲くのでそのように呼ばれるのだが、唐子咲きの椿は、卜半(ぼくはん)と呼ばれることが多く、私の家には赤色の唐子咲きの紅卜半という種類の椿もあり、それは4月に咲く。楼蘭花は1月から咲き始める。ピンク色なので、さしずめ桃卜半とでも言うべきだが、ピンク色の唐子咲きの種類も多い。桃色卜半という種類もあり、ネットで見ると、それも美しい。ピンク色にも様々な色合いがあるが、我が家の楼蘭花のピンク色は、写真で見てもわかるが(わかってほしいが)、上品な色合いであり、咲き進むとバラで言えば美人の代名詞のロイヤルハイネスのピンク色に近くなる。
楼蘭花の写真は、今やネット検索をするといくつも出てくるが、ひいき目で見るせいか、我が家の庭の楼蘭花ほど美しいものは見たことがないように思う。我が家の楼蘭花はオシベが綺麗に揃っていて、周りの花弁の大きさと広がりも絶妙である。また、練馬の寒い冬にも負けず、花弁が寒さに焼けないで開いてくれる。ピンク色の椿に西王母という種類もあり、これは10月頃から咲き始める早咲きの椿で、その頃に咲くとこれまた上品な姿を見せてくれるのだが、昨年秋はほとんど咲かず、12月頃から咲き始めた。しかし、西王母はユキツバキ系で、練馬の乾燥した冬は合わないらしく、咲き出しても縮こまってしまい、登山家の雪焼けした顔を思わせるかわいそうな姿となった。
楼蘭花は、茅ヶ崎市の氷室夫妻が肥後椿の御国の誉という種類の自然実生から作出されたものと言われている。肥後椿は、長いオシベが花全体を覆うような独特の花型であり、唐子咲きとは似ても似つかないので、本当に御国の誉から作出されたの?と信じられない。このようなこともあることから、椿の新品種作りに多くの好事家が熱中するのだろう。楼蘭花の苗を庭に植えつけた頃、氷室夫妻の椿園を茅ヶ崎に訪ねたことがある。その椿園は一般に開放されていたが、どこか余裕を感じさせる庭だった。楼蘭花の作出は、好事家というより、椿を愛する人の手にたまたまふれて自然が創出した奇跡的なできごとだったのかもしれない。