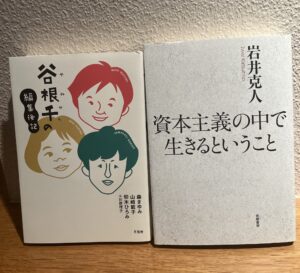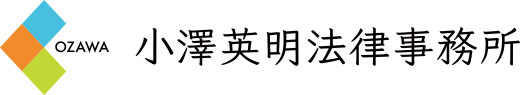売れること (2025年4月)
2025年4月21日
小 澤 英 明
先日、書店の新刊コーナーで岩井克人「資本主義の中で生きるということ」(筑摩書房)を見つけた。中をパラパラと見ると、「『高慢と偏見』と資本主義の倫理」とあるエッセイがに目が止まった。「高慢と偏見」は、ジェーン・オースティンの有名な小説だが、その大筋を紹介しつつ、資本主義の論理は、「売れなければならない」というものだが、資本主義の倫理は、「売れればよいというものではない」というものだとの指摘があった。岩井氏のこの本の中には、「『自己疎外』と資本主義の論理」と題するエッセイもあり、これもあわせ読むと、岩井氏の資本主義に対する見方がよくわかる。
私の世代は、岩井氏から10年ほど遅れているため、学生運動には無縁の者ばかりで、「自己疎外」などという言葉とも無縁であった。「それはお前が無知だったからだよ」と言われれば、そうかもしれないが、あの狂乱の学生運動の渦に巻き込まれなかったことは、私たち、遅れてきた世代にとっては幸せなことだったと思える。中国の文化大革命の映像は、私たちの中学生の頃、頻繁にテレビで流れていた。紅衛兵が知識人に三角帽など被せて罵詈雑言を浴びせている様子は、見るに耐えず、主導したと言われる毛沢東という男は、とんでもない男だと嫌悪感を覚えた。日本の学生運動にも同様の嫌悪感を感じたこともあった。どうして、このようなことが起きたのかとの疑問が生じる。
岩井氏は、社会主義体制は、ひとつの例外もなく人間の自由と独立を抑圧する独裁体制に帰結したことを指摘して、それは、社会主義体制は、みずからの独善性に対する内側からの歯止めをもつことが不可能だったからだと、述べている。これが前述の疑問に対する本質的な回答であると思う。資本主義社会では、売れないと生きていけないが、だからこそ、「俺、何で売れないんだろう」と、反省をいつも迫られるのである。しかし、人間は、売れれば何でも良いと思っているわけでもない。このことをオースティンは、「高慢と偏見」の中で、エリザベスがダーシーの求婚を断ったことで、示してくれているということを岩井氏は指摘しているのである。これが、資本主義の論理の歯止めの倫理なのであり、その歯止めが機能するからこそ(資本主義はこの歯止めを否定はしない)、不完全でも資本主義に価値があるわけである。
と、やや硬い話になったが、森まゆみ、山崎範子、仰木ひろみ、川原理子の「谷根千の編集後記」(月兎舎)に、「おとなになるってことは、想像力を働かせて、いろんな状況があるってことがわかって、周りとうまくやることなんだ。だけど、『私もガマンするからアンタもガマンして、うまくやりましょう』的なのは好かない。『私はこうするけど、アンタは何が言いたいのよ』的にうまくつきあっていくのがよい。会いたくない奴と会って、話したくない奴と話して、したくない仕事をして、一生を終わりたくないものなァ。」という言葉があった。こういう構えで、それぞれが生きていける社会が、いい社会なのではないか。