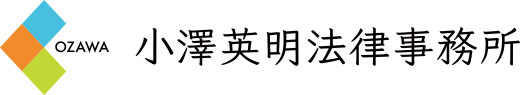都市プランナーの雑読記 その103
阿南友亮『中国はなぜ軍拡を続けるのか』新潮選書、2017.08
2025年10月10日
大 村 謙二郎
本書の著者紹介によれば、阿南は1972年生まれで、慶應大学を卒業後、大学院在籍中に北京大学国際関係学院に留学、現在は東北大学大学院法学研究科の教授である。専門は政治学、中国研究。
著者あとがきによれば、阿南は父の仕事の関係で小さいときから中国に暮らしていたこともあり、大学で中国研究者になることを決意してから、中国に留学し、現地でフィールドワークを行ってきた中国通で、たんなる文献学者ではないようだ。多分、中国語の読み書き、会話にまったく不自由はないのだろう。中国、欧米にも広く、深いネットワークを持っていると思われる。
本書は軍事面での情報分析も詳細だ。ネットで見ると阿南は、父親は中国大使も務めていた外交官で父の仕事の関係で中国に暮らした経験を持っているとのこと。さらに彼の祖父は陸軍大臣で、日本のいちばん長い日の8月15日に自決した阿南惟幾(あなみこれちか)であるとのことで、阿南家の系譜の華麗さに感嘆した。
本書であるが、阿南の立場は現在の中国共産党独裁で党の私兵組織として機能している人民解放軍のあり方についても批判的である。
中国は国民の政治参加がまったく許されない、一党独裁の非民主国家であり、この間、鄧小平の指導の下で中国が進めてきた改革・開放路線は多くの問題、矛盾を抱えており、西側社会が中国の民主化が進み、欧米、日本との対等で公平な交流が出来るということはほとんど進められなかったと断じている。
本書の特色は、長年、人民解放軍の分析を活かした記述で、なぜ中国共産党が、解放軍を私兵化し、解放軍も共産党との共生関係を結び、利権を得ようとしているかについて、わかりやすく解説している。軍拡の泥沼の問題や構造を、毛沢東以来の権力闘争、軍組織の関係等についての緻密な分析をおこないながら論を展開している。
阿南によれば人民解放軍の軍備、軍事力は仮想敵国である米軍の軍事力に対して、相当遅れており、脆弱性を抱えているとのことだ。軍事技術、軍事専門家の育成、開発にも多くの脆弱性を抱えているとのことだ。2017年の刊行の書で、その後、中国が劇的に進化、変化したのか、不明だが、中国の軍事大国化をそれほど恐れる必要がないことなどを論じている。どこまで、信用していいのか、わからないし、ある種の保守派の国防強化論かなとも思うが、なかなか、説得力のある論であることは確かだ。アメリカは軍需産業の要請や軍事に利権を持つ政治家、経済人の思惑もあって、アメリカをある面で、中国の軍事力が上廻っているなどの中国軍事脅威論がことさらに強調される傾向があるのかも知れない。このあたりの機微はよくわからないが。
阿南のこの書を読むと、中国では近い将来に体制が崩壊し、民主的な体制に転換するということは絶望的だなと感じる。一方で現況の共産党独裁、専制統制ぶりを、暗黙裡に容認している多くの民衆がいることは確かだ。また、比率的には少ないが、共産党との関係をつなぎ、利権を得ている膨大な関係者、新興財閥、富裕層、軍関係者集団がいることも確かで、こういった存在が現政権を暗黙裡に支えているし、また、共生関係を結んでいるのだろう。
社会経済の変化が激しい中国であるが、一方で深層の構造はそう簡単に変化しないのかもしれないし、何よりも長い中国の歴史の中で言えば、現代中国はほんのわずかな時間であり中国観察も表層の変化に目を奪われないことが必要なのだと思う。