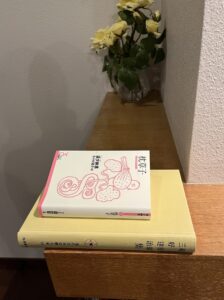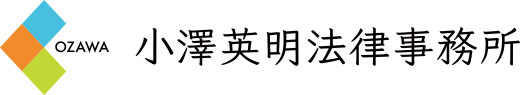説教の講師は (2025年10月)
2025年10月7日
小 澤 英 明
先月、美しい優しい女性の夢の話を書いたので、数少ない女性の読者には面白くなかったものと思う。というわけで、罪滅ぼしに、ギャフンとさせるわよ、みたいな話をとりあげる。何も大げさなことを書く必要もないのだが、竹西寛子さん(1929-)が女性文学者の佐々木和歌子さん(1972-)を褒めておられたので興味をもって、佐々木和歌子さんが翻訳されている「枕草子」(光文社古典新訳文庫)を買ってみた。すると、その現代語訳がなかなかで、もちろん清少納言(966年頃-1025年頃と言われているがはっきりしないようである)の原文が良いのだが、三十一段に「説教の講師は」というものがある。その最初のくだりを引用すると、次のとおり。
「説教の講師は、顔がいい人を希望。だって、顔がいいと講師をじっと見つめてしまうから、説教の尊さがしっかりと伝わってくるのだ。よそ見をしていればふと内容も忘れちゃうのだから、ぶさいくな顔の講師は罪を犯しているのと同じ。というようなことは書かないでおこう。もう少し若かったらこんな罪深いことも平気で言ってしまうけれど、この年齢ともなると仏罰がとても怖い。」とある。さすがに清少納言。手もとの鏡に映った自分の顔をじっと見る。パサパサの白髪頭。これでよくセミナーの講師などつとめているものだ。
気を取り直して、枕草子の面白そうなところを拾い読みする。三十五段に「木の花は」で始まる段に、清少納言の好きな木の花が書かれている。紹介すると、紅梅、藤の花、橘、梨の花、桐の木の花、楝(おうち)の花。このうち、梨の花は、かねてから気になっていたのだが、現物を見たことがない気がする。清少納言によると、「花びらの端に美しさがほのかに匂うようだ。玄宗皇帝の使者が見た冥界の楊貴妃は、その泣いた顔が『梨花一枝、春、雨を帯びたり』ー 一枝の梨の花が、春の雨を含んだようだったー と表現されたのだから、その扱いはなみなみならぬもの。そう思えば、やはり唐の人からすると梨の花はだんぜん特別な花で他とくらべようもないものだな、と合点した。」とある。スマホで梨の花の写真はいくつも見られるのだが、いくら画素数の多いわがスマホでも花びらの端にほのかに匂うような美しさまでは捉えきれていないように思う。来年春に現物を見るしかないように思う。
梨の花が気になっていたのは、三好達治(1900-1964)の「願わくばわがおくつきに/植ゑたまへ梨の木幾株(しゅ)// 春はその白き花さき/秋はその甘き実みのる// 下かげに眠れる人の/あはれなる命はとふな・・・しかはあれ時世をへつつ/墓の木の影をつくらば// 人やがて馬をもつなぎ/旅人らここにいこはん・・・」という有名な詩に、梨の木がうたわれているからである。「おくつき」とは、奥津城、すなわち、神道の墓のことで、谷中霊園に行くと、「○○家の墓」と刻まずに「奥津城」と刻む墓も少なくない。ドイツにリベックじいさんの梨の木という童話があることは、三好達治のこの詩にふれた中野孝次(1925-2004)のエッセイで読んだ。心やさしいリベックじいさんが、屋敷の中の梨の実を秋になると近隣の子供たちに分け与えていた。死ぬ間際に、自分が死んだら梨を墓に埋めてほしいと、言って亡くなった。しかし、欲張り息子が墓の周りに柵を巡らせた。それでも、大きく梨は成長して、たわわに実った実は墓のそばを通る子供たちに再び恵みをもたらしたというもの。
果物で好きなもの、梨。