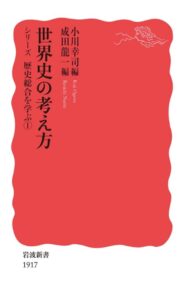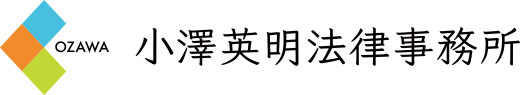都市プランナーの雑読記 その102
小川幸司編・成田龍一編『世界史の考え方』シリーズ歴史総合を学ぶ①、岩波新書、2022.03
2025年9月12日
大 村 謙二郎
高等学校の新科目に「歴史総合」が加わるということで、それにあわせて、企画されたシリーズの第1巻が本書。成田は大学で歴史学を教えていた人、小川は長野県の高校校長で歴史教育などに関する著作、論文の多い人。
本書は、近世・近代以降の世界史をどう理解できるかについて3部、5章構成で展開している。各章で扱う時代、テーマに関連する3冊の歴史書を取り上げて、それを読み解きながらその時代の世界史、日本との関わりなどを説明し、また、各章ではそれぞれの分野の歴史専門家を招待してその人の著作、専門を解説してもらいながら、鼎談を行うという構成となっている
第1部は近代化の歴史像と題して2章構成で歴史を読み解いている。
第1章は「近世から近代への移行」で課題図書は、大塚久雄『社会科学の方法』(岩波新書1966)、川北稔『砂糖の世界史』(岩波ジュニア新書1996)、岸本美緒『東アジアの近世』(山川出版社1998)の3冊だ。この課題図書を読み解きながら、中国近世史が専門の岸本を招き、近世から近代への移行をどう捉えるかを議論している。
第2章は「近代の構造・近代の展開」で課題図書は次の3冊。
遅塚忠躬『フランス革命』(岩波ジュニア新書1997)、長谷川貴彦『産業革命』(山川出版社2012)、良知力『向こう岸からの世界史』(ちくま学芸文庫1993)
国民国家をどう捉えるか、フランス革命の光と影、明治維新との比較、イギリス紙から見たこのテーマをイギリス近現代史が専門の長谷川を交えて鼎談を行っている。
この章は比較的なじみのテーマで分かり易い。
第2部は国際秩序の変化と大衆化の歴史像で3章と4章があてられている。
第3章は帝国主義の展開で、課題図書は次の3冊だ。
江口朴郎『帝国主義と民族』(東大出版会、新版2013)、橋川文三『黃禍物語』(ちくま書房1976,岩波現代文庫2000)、貴堂嘉之『移民国家アメリカの歴史』(岩波新書2018)
ナショナリズムの捉え方について、課題書を読み解きながら、江口については、資本主義と国民国家形成・帝国主義の同時展開、階級、民族、ナショナリズム、それぞれの世界史、自分を問いなおす世界史について語っている。次に橋川の黄禍論を取り上げ、異色の帝国主義論、人種主義が流行する要因を探る必要性、人種と民族と国民について語っている。
次に貴堂をゲストに「アメリカ史から見ると」と題して、「帝国」としてのアメリカと国民形成、民族国家としての国民国家形成とウィルソンの「民族自決」、カリフォルニアの日系移民、raceという概念、戦後歴史学における「人種」の不在について、語っている。さらにアメリカの移民国家の複雑さ、多くの矛盾・問題点を内包していることを語り合っている。アメリカ近現代史を違った観点から見ると同時にかつての明るいアメリカ史とは違う側面があることを指摘している。この章の議論は啓発的だ。
第4章は20世紀と二つの世界大戦がテーマで、課題図書は次の3冊だ。
丸山真男『日本の思想』(岩波新書1961)、荒井信一『空爆の歴史』(岩波新書2008)、内海愛子『朝鮮人BC級戦犯の記録』(勁草書房1982,岩波現代文庫2015)
総力戦の捉え方、アフリカ史(永原洋子)から見ると、永原洋子との対話からこの章は構成されている。
第5章は現代世界の私たちが主題となっている。課題図書は次の3冊。
中村政則『戦後史』(岩波新書2005)、臼杵陽『イスラエル』(岩波新書2009)、峯陽一『2100年の世界地図 アフラシアの時代』(岩波ジュニア新書2019)
グローバル化の捉え方、中東史(臼杵陽)から見ると、臼杵陽との対話の構成となっている。
4章、5章は私にとってなじみのない地域の歴史であり、歴史観も含めて、あまり頭に入らなかった。再読する必要がある。
意欲のある高校生ならば読み通せるかも知れないが本書の議論は歴史観、歴史認識などを含んだ抽象的議論も多く、理解するのが困難な議論も多い。各章で課題が出されているがこれをちゃんと答えることが出来るのかというと難しい問題だ。私自身も課題図書で挙げられている本には未読のものが多い。はたして、これにすべて挑戦できるかというと、いささか気が萎える。