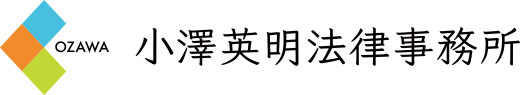清福について (2025年8月)
2025年8月15日
小 澤 英 明
事務所運営において、日頃から何か気をつけていることがあるかと言うと、とりたてて言うこともないが、請求書については、受け取った日か翌日には払うことにしている。これは、中野孝次(1925-2004)の「清貧の思想」のなかで、本阿弥妙秀(1529-1618)の話として、支払いを年末ギリギリに行う慳貪な富者を妙秀がひどく嫌うくだりがあり、これが心に響いていたからである。したがって、支払いはきれいな方だと思うが、最近、カードの支払い額確定という偽メールがいくつも来るようになって閉口している。とんでもない世の中になったものである。妙秀が知ったら何と言うか。
先日、森鷗外(1862-1922)の「ヰタ・セクスアリス」をおもしろく読んでいたら、鷗外の15歳の頃の漢文の文淵先生の話があった。その先生を鷗外のお父さんが、「あれが清福というものぢゃ」と羨ましがっていたとのくだりがある。「清福」の言葉の意味を調べると、「清貧」の意味と似ている。ただ、「清貧」と言うと、「貧」の字が入るのでどうしても敬遠したくなる。「清貧」の人は尊敬すべきだが、羨ましい人とは言えないだろう。「清福」の方が語感がいい。しかし、「清貧」も「清福」も、今や目にする機会の少ない言葉になってしまっている。ところで、この自伝的小説の中には、文淵先生の机の下に唐本の「金瓶梅」があるのを鷗外が見つけて、「先生なかなか油断がならない」と思ったとも書かれている。
この文淵先生とは、解説書など読むと、依田学海(1834-1909)のことである。依田学海と知って、これは、正宗白鳥(1879-1962)の「内村鑑三」の本の中にあった先生ではなかったかと、白鳥の本をとりだした。その中に、白鳥が、依田学海と上田敏(1874-1916)とともにある会食に呼ばれたときの話がある。「雑談のうちトルストイの徹底的非戦論が出ると、翁は、『口先で話が極まらなければ、腕ずくで勝負をつけるより外、為方がないじゃないか。』と口角泡を飛ばして論じた。『トルストイは先生より年下ですよ。』と上田が云うと、『そうか、年下のくせに生意気だ。学海先生のお説を聞きに来い。』と、ふざけた口を利いて一座を笑わせた。」とある。このやりとりは、白鳥のこの本を読んだときから、私の頭の中に深く刻まれている。学海先生は、酸いも甘いもすべてお分かりなのだ。
斎藤希史教授(東大)の「漢文スタイル」(2010年、羽鳥書店)というエッセイ書の中に仲長統(180-220)の「楽志論」という書の紹介がある。そこには、「良い田と広い家、山を背にして流れに臨み、周囲に堀や池を巡らせ、そこかしこに竹や木を植え、畑地もあり果樹園もあり、舟や車も備えて使用人もいる。親にはごちそうを差し上げられ、妻子を苦労させることもない。友が集えば酒肴をつらねた宴、節句には子羊や豚を煮る。あぜ道をぶらぶらし、林に遊んで、清水で足を洗い、鯉を釣り、雁を捉え、舞萼(ぶう)の下で涼んで、口ずさみながら帰るのだ。」というような世界が夢想されているとのこと。文人が理想とする生活風景などとも言われているようだ。しかし、広大な家屋敷に豊富な食物、お世話をしてくれる使用人もたくさんいそうである。夢の世界だが、そこまでどうやってたどりつくのだろうか。