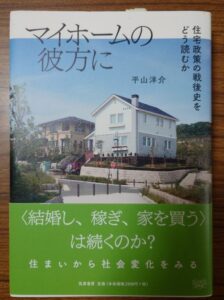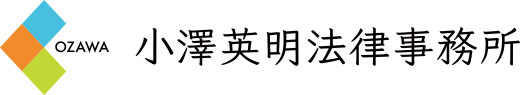都市プランナーの雑読記 その100
平山洋介『マイホームの彼方に 住宅政策の戦後史をどう読むか』筑摩書房、2020.03
2025年7月22日
大 村 謙二郎
住宅政策研究について、数多くの著作、論文を執筆し、国際的にも活躍している平山の著作である。内容的にずっしりと重く、論理、分析も緻密で圧倒される著書だ。
平山は本書では住宅政策、住宅制度、それを支えるイデオロギーなども含めた総称として住宅システムという言葉をつかっている。そして、住宅システムが歴史的、空間的違いを持つことを踏まえた分析の必要性と正当性を論じながら、戦後日本の住宅政策を丹念に分析し、マイホーム社会という夢が幻想、幻滅となった現代日本の状況を踏まえてどのような住宅システムが求められているかを論じている。
「はじめに」と「おわりに」挟んで6章構成となっている。
「はじめに」においては、本書を貫く問題意識として、ポスト成長時代の日本の住宅システムが大衆化から再階層化へ大きく転換していること、その軌跡をたどることの必要性を明らかにしている
第1章、第2章は本書の理論的枠組みや日本の住宅システムについて整理して、以降の章の導きとしている。すなわち、1章では「住宅所有についての新たな問い」として、持ち家、賃貸等の住宅テニュアの違いが社会システムにどう影響を与えているのか、について整理している。
2章では「住宅システムの分岐/収束」として、国際比較の中で日本の住宅システムであるデュアリズムの特質と近年の新自由主義=ネオリベラリズムの隆盛の中で、住宅政策がどう影響を受けているかについて論じている。
3章から5章までは3期の時代区分毎の日本の住宅システムが時代環境の変化の中でどう変容してきたのかを詳述している。多くの統計、データを駆使しながら、いかに日本の住宅政策が持ち家政策に傾斜していたか、公共賃貸住宅がどんどん痩せ細り、また、これを補完する民間セクターの脱商品化した賃貸住宅・社宅がいかに減少、変化していているか、人口、世帯の変化と絡めて、精緻に分析してる。
おわりにでは「新たな「約束」に向けて」と題して、本書全体をまとめると同時に、戦後の高度成長期に一億層中流化の持ち家社会の実現が社会の安定と繁栄をもたらすといった夢が、無残な幻影に過ぎなかった中で、ネオリベラル・ファンタージーを打ち破り、社会政策としての住宅政策・住宅システムを再構築することの必要性と提言を行っている。
簡単に要約できるような内容の本ではないが、平山の熱い情熱と精緻で冷静な分析が合わさった充実した内容の本であった。平山は独特の用語を駆使し、レトリックも巧みで文章も理解しやすい。
ただ持ち家政策批判はもっともと思うが、多くの先進諸国や脱社会主義化したかつての社会主義諸国が総じて、公共賃貸住宅供給政策から撤退し、持ち家政策に傾斜した意味や、それが社会経済の安定、発展と繋がってきているとの主張に対して、どう対抗する、新たな公共住宅政策を構築できるかが、問われていると感じる。
もう一度、ノートをとりながらじっくり読んだ方がよい内容の本だ。