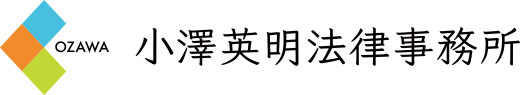コラム第34回
続・私が住んだところ(その4)-パリ、ブローニュ・ビヤンクール(子育て編)-
2025年7月22日
早 水 輝 好
日本では梅雨を飛ばして早くも暑い日が続いているが、ヨーロッパはさらに上を行く猛暑らしい。スペインでは40℃を超え、パリでも40℃近い日があるとか。想像できない暑さである。30年前のパリではエアコンなどなかったが、せいぜい昼間30℃を超えるぐらいで熱帯夜もなく、特に問題はなかった。今はどうなのだろうか。
今回のコラムは前回の続きで、パリでの子育てのあんなこんなを振り返ってみる。
環境省からパリのOECD事務局に赴任した1993年12月時点で長男は6歳、次男は3歳。日本にいれば翌年の4月から新一年生と3年保育の年少組に当たる年齢であり、子供たちの教育をどうするかは悩ましかった。最近の赴任者はインターナショナルスクールに子供を入れることが多いようだが、当時は「インターは費用がかかる」と聞いていて、初めから考慮外だった。現地の学校は9月始まりですでに新学年に入っていたこともあり、長男は日本人幼稚園に3か月だけ入れて、4月から日本人小学校に行かせることにした。他方、次男は、「幼稚園はどこでもいつからでも同じだろう」と考え、現地の幼稚園に入れることにした。
小中学校合同の日本人学校はパリ近郊のサン・カンタン・アン・イヴリーヌいう街にあった。もともとはパリ市内にあったのだが、手狭だからと引っ越したとのこと。市側は日本人学校を誘致すれば日本人もたくさん住むようになると期待したらしいが、結局多くの日本人はパリにとどまり、子供たちはスクールバスで通学して、先生方だけが住んでいるとのことだった。徒歩圏内に鉄道の駅があったので、車を運転できるようになるまでは、行事や面談の際には鉄道を使った。
敷地は広々としていて、クラスの人数もそれほど多くなく、良い環境だった。また、中学生も含む9学年が同じ敷地で学んでいたので、上級生の面倒見がよいと言われていた。私は記憶していないが、家内によれば、小中合同の入学式で「起立!」と先生が言ったら新中一生は立ったが新小一生はキョトンとしていて、すぐに先生が「立ちましょう」と言ったらおもむろに立ちあがり、ほほえましかったとのこと。運動会も9学年合同で行われ、PRのためか幼児向けのかけっこもあったので次男も参加した。
スクールバスにはいくつかのコースがあり、乗車時間に乗車場所に連れて行けばよかった。ただ、親が交代で付き添い乗車することになっていたので、結構細かい調整が必要だった。乗車予定だった家内の具合が悪くなって急遽私が乗ったこともあった。
次男は近所の幼稚園なので楽だったかというと、実はこちらの方が結構大変だった。フランスでは10歳以下の子供を一人にしておくのは法律で禁じられていて、通園は当然親同伴である。日本では私学に通う小学生が電車に乗っている光景が見られるが、フランスではありえないことだった。下校時間に迎えに来られない共働き家庭の子供のためには、日本で言う「学童保育」にあたるギャルドリーというシステムがあって、夕方に先生が入れ替わって学校で面倒を見ていた。
我が家の場合、朝は私か家内が送っていき、帰りは家内が迎えに行くことで問題はなかったが、昼食という難関があった。幼稚園で昼食を食べさせられるのは基本的に共働き家庭で、母親が専業主婦の場合は家で食べさせるというルールだった。このためどうなるかというと、私が出張などで対応できない場合、家内は朝の送り、昼の迎え、昼食後の送り、夕方の迎えと、1日4回幼稚園を往復することになった。ちょっとパリ市内へお買い物、というのも簡単にはできなかったのである。
また、幼稚園でも「体育」としてプールやスケート場に行くことがあり、手が空いている親のお手伝いが期待されていた。家内も時々顔を出し、次男の友達から「Yoshiaki のMaman(母)は何を言ってるのかわからない」と言われながらお手伝いをしていた。
次男は最初こそ泣いたりしていたが、だんだん慣れていった。半年ほどで年中組に上がったら「彼はあまり話をしないが、言われたことはだいたいわかっているようだ」と先生から言われるようになった。年長に上がったら自分からも話すようになり、最後の年は、日本より半年早く始まった小学校1年生のクラスを全うすることになった。
一番印象に残っている行事は年長組の時の「お泊り保育」である。ブローニュ市がロワール地方に持っているシャトー(古い城屋敷)に幼稚園から行くのだが、話を聞くと「10泊11日」というではないか。先生のところに相談に行ったら、「そのぐらいが親からの自立を経験するのにちょうど良い期間。Yoshiakiは話ができるから問題ない」と言われた。腹をくくって放り込んだら、11日目に帰ってきて、親が迎えに集まっている中で、バスから子供たちが降りてくるのと同時に、お土産のワインとチーズが配られた。さすがフランス、と思わずにはいられなかった。後で聞いたら、途中で発熱したが、回復して帰ってきた、ということだったらしい。詳細は不明のままである。
フランスでは学校以外の教育にも力が入れられていた。そもそも学校は月・火・木・金の週4日で、水曜日は運動系・文科系・語学系などの課外活動があって希望者が申し込み、参加費は納税額によって異なる(高額納税者ほど参加費が高い)というシステムだった。次男も途中からスポーツ系の活動に参加した。また、フランスは夏休み、秋休み、冬休み、スキーバカンス、春休み、5月の長い週末とお休みが多く、そのたびに課外活動のカリキュラムが組まれ、同様に申込制になっていた。最後の春休みに次男はフランス中部で開催される子馬乗馬教室に行きたいと言い出し、私が朝7時に市役所に並んで仮申込みをした。人気のカリキュラムは厳しかったようで、「『イギリスでの英語学習』は定員に達しましたので締め切ります。」とアナウンスが流れ、私の数人前に並んでいた男の子がうなだれて帰っていった。
後日、正式な申込みに市役所に行き、英語ができる人が応対してくれたが、そこでの質問がすぐには理解できなかった。自宅を記入しているのに、「緊急時の連絡先を教えろ」というのである。連絡先って自宅に決まっているだろう、と思ったとたんに気づいた。そうだ、フランスでは子供を送りだしたら親もバカンスに行くから、連絡先が自宅とは限らないのだ。フランス文化を垣間見た気がした。
1週間の乗馬教室を終えて、次男は無事に帰ってきた。持っていった馬のぬいぐるみをとられそうになって引っ張ったら鞍がとれてしまって大泣きし、先生がくっつけてくれたということがあったらしいが、これまた「真相は藪の中」である。
フランスでは子供に厳しい。エレベーターで次男がボタンに触ろうとしたら同乗していたお年寄りに「そんなことをさせてはいけない」と厳しく注意されたとか、レストランは犬は静かにしているので入れるが子供は騒ぐので入れないとか、不便が多かった。しかし、逆に子供たちを支え、自立させるシステムはしっかりしていて、特に次男には良い経験になったのではないかと思っている(残念ながらフランス語は帰国後2週間で忘れてしまったが)。
いろいろなことを経験したフランスでの滞在も、任期満了の時期を迎え、帰国することになった。最後の夏に、日本の国家公務員の重労働を知っている同僚から「生涯最後のバカンスだな」と言われた束の間のギリシャ旅行を楽しんだ後、1997年8月23日に帰国の途についたのである。
早いものでフランスから帰国して30年近い時が流れ、その後出張では何度か行ったが旅行では訪れていない。当時の「フランス人気質」は今も残っているのだろうか。ぜひ再訪したいが、退職してすぐに行けばよかったのにもたもたしているうちにコロナに突入してしまい、家内の熱も一気に冷めてしまったようだ。でもできるならもう一度ゆっくり訪れてみたいところである。
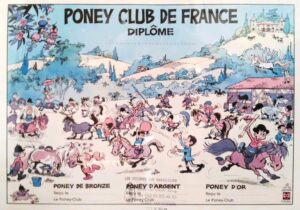
子馬乗馬教室の認定証(Poney d’argent: 銀賞)