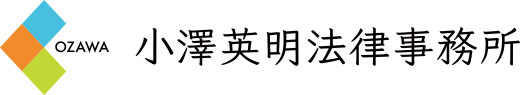都市プランナーの雑読記 その99
刈谷剛彦・吉見俊哉『大学はもう死んでいる? トップユニバーシティーからの問題提起』集英社新書、2020.1
2025年6月30日
大 村 謙二郎
教育問題、大学問題について数多く発言している、同世代の社会学者の二人が、大転換期にある、大学のあり方、将来について対談したのが本書である。
刈谷の勤務するオックスフォード大学の研究室で4日間にわたって対談した記録を編集してできあがったものだ。
第1章では大学で何が問題となっているかが扱われている。国内ではトップ大学と目されている東大が凋落し、優秀な学生から蹴られる時代になっていることの遠因、原因、日本の大学の作られ方の特殊性、キャッチアップ型大学であったことの特質をオックスフォード大学との対比で論じている。
第2章では「集まりの場としての教室」として、東大、オックスフォード大学、ハーバド大学に在籍する学生の知的レベル、能力に差はないが、教育のあり方の違いなどを論じている。オックスフォード大学でのチュートリアル制度が守られていることの意味、意義を論じている。
第3章は、「社会組織としての大学」が論じられている。カレッジ、ファカルティ、ユニバーシティーの違いを論じながら、日本の大学がユニバーシティーの体をなしていないことの問題などを論じている。
第4章は「文理融合から文理複眼へ」をいうテーマが扱われている。文系廃止論の問題、人文知が必要とされることの意義について吉見が年来の主張を論じている。刈谷は言語の問題を論じている。二人ともグローバル言語としての英語の必要性を論じているが、それだけで収まるかも含めて、表層的なグローバリズムに批判的で、この点は同感できる。
第5章は前章を受けて、「グローバル人材」と題して、グローバリゼーションと知識労働、大学の役割などが論じられている。グローバルキャピタリズム、グローバルアカデミズムの波に抗しきれない中で、いかに対抗するかが論じられている。
吉見が企てた、東大独自のグローバルリーダー育成プログラムについてはその、努力、情熱はすごいと思うし、トップエリートを育成するやり方はそうなのかと思う一方で、すべての大学がこういった方向を目指すべきだと思わない。日本近代が育成してきた、厚みのある中間層の育成に対して大学が果たしてきた役割をどう考えるのか。グローバル人材となにかを深く考えさせられる。
第6章は都市空間としての大学で、吉見お得意の都市論に引き寄せて、キャンパスの物理的空間の意義とネット時代のキャンパス、大学の果たす役割がどうなるのか、丁々発止の議論が展開されている。
二人とも現状の動向に悲観的、批判的であるが、批判の保守主義化を問題として、楽観主義的展望を語っている。ある種のクリティカルオプティミズムが大切なのかもしれない。
私などは大学とは無関係になって久しいが、それでも日本の行く末を考えたとき、時代を担う世代が日本という場を出発点として、どう育っていくのか、社会を形成していくのか、その上での教育・研究機関の大学の役割がどうなるのかには関心がある。これからの教育、大学のあり方を考えさせてくれる、刺激に満ちた本だ。
コロナ禍で、大学での授業がリモートになり、大学での教育のあり方が大転換した時点以前での議論であり、その後の生成AIなどの発展によって、大学の教育、研究が大きく揺らいでいる時代のことは扱われていない。しかし、これからの高等教育のあり方、大学の果たす役割を考える上での本質的な論点は提示されており、今でも読む価値のある本だと思う。