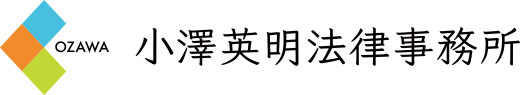ピアソラとヴィラ=ロボス (2025年7月)
2025年7月2日
小 澤 英 明
若いときから、いろいろとクラシック音楽を聴いているが、このところは、YouTubeで適当に聞き流しているおかげで、これまでほとんど聞いていなかった音楽を耳にして好きになってゆくことがあり、楽しい。加齢とともに感受性もひからびるのでは悲しいが、音楽に対する感受性はそうでもないようだ。これから膨大なまだ聴いていない曲を聴いてゆけると思うと、うれしくなる。これまでほとんど聴いていない作曲家としては、南米の作曲家がいる。アルゼンチンのピアソラ(1921-1992)とか、ブラジルのヴィラ=ロボス(1887-1959)とか。ピアソラのオブリビオンは、かねてからいい曲だなと思っていたが、先日、「チキリン・デ・バチン」という曲(バチンという酒場に出入りしていた花売りの少年を歌ったもの)が流れてきてすごく好きになった。
このところ、よく聴くのは、ヴィラ=ロボスの曲。ある日、ピアソラの曲を聴いていたら、YouTubeが、これはどうですか、とお節介で、ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ」を流してきた。この曲名は、かねてから知っていたが、偉大なバッハ様を汚しているようで、手を出していなかった。広島風お好み焼きとか、このナントカ風という言葉は好きではない。しかし、この「ブラジル風バッハ」の第5番のアリアの音楽がテレビから流れてきたとき、一瞬で好きになった。
まだ、そんなに聴いてはいないので、ヴィラ=ロボスについて何も語る資格もないのだが、好きという気持ちに偽りはなく、好きなら好きと好きになったその日から大声で言ってもよいはずである(本当に?)。もっとも、バッハやモーツァルトやシューマンに対する「好き」とは、かなり違った気持ちである。若い頃ならば、吉田秀和はこのヴィラ=ロボスのことをどう評価しているのかなと、つい本を出して調べ始めたはずだが、少しも心にひびかなかったからか、吉田秀和がヴィラ=ロボスについて何か書いていたような記憶はない。ピアソラについてもなかったような。それを思うと、自分の審美眼にとたんに自信がなくなる。ただ、ヴィラ=ロボスと同じブラジル生まれのネルソン・フレイレ(ヴィラ=ロボスの曲を多く弾いている)やピアソラと同じアルゼンチン生まれのバレンボイム、アルゲリッチについては、吉田秀和は若いときから絶賛していたので、どこかで触れているかもしれない。
この二人の作曲家の曲のどこが魅力的なのかは言葉にしにくいが、刺身を醤油につけて、ああ、うまいと口にだすような男にはとても浮かびそうもない曲想で、要するに地球の裏側にある南米の国々を思わせてくれるエキゾチックな魅力なのである。リオデジャネイロやブエノスアイレスの港を見下ろす小高い丘の中腹で、真夏の夜に家の外のベランダに出て眼下の夜景を眺めていると流れてくるような曲調と言うべきか。きっと少し涼しい夜のそよ風が吹いてくる。そこに功なり名を遂げた一人のスマートな老弁護士が美女にもててチヤホヤされた昔を思い出し、ベランダの欄干に手をかけてワインを飲む。いいなあ。
 リオデジャネイロの夜景
リオデジャネイロの夜景