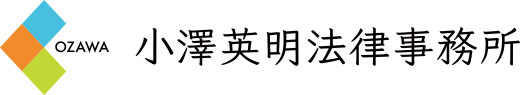都市プランナーの雑読記 その98
岡本隆司『李鴻章-東アジアの近代』岩波新書、2011.11
2025年6月17日
大 村 謙二郎
中国近代史が専門で、中国の近現代史に関する著作だけでなく、中国史全般や東アジアの近現代を世界史的視点から叙述した本も多数刊行している岡本隆司の李鴻章に関する評伝である。
新書だが、清代の中国社会、官僚選抜システムとしての科挙とその昇進の仕組み、地方政府と科挙官僚の関係等を解説しながら、清朝末期に活躍した李鴻章について詳しく述べている。
李鴻章が魅力的な人物であったかはわからないし、それほどエピソードのある人ではなかったようだが。日本でいえば、幕末から明治初期にかけての時代に、清と日本との関わりについて、重要な役割を果たした政治家李鴻章をその関わった事件、課題との関係でわかりやすく解説している。
中国の世界観としての華夷秩序と周辺国を属国と扱っていたことが19世紀に西欧諸国との対応の中で、その見直しが迫られ、多くの矛盾が出てくる中で、優秀なまた国家意識の強い李鴻章が洋務運動を提唱したこと、近代的な軍政、軍備を備えることに傾注したことが描かれている。しかし、なかなか、それがかなわなかったこと、当時の日本をどう、李鴻章は認識していたか、清朝が終末を迎える中での李鴻章の果たしたこと、果たせなかった役割などが描かれている。
李鴻章については日清戦争終結後の中国にとって屈辱的な下関条約の中国代表だったくらいの知識がなかったので、19世紀後半の中国、日本の動きを歴史的に理解できて良かった。明治政府が台湾侵攻や琉球処分を行い、ある意味で帝国的自立をとげたあたりは、清や朝鮮にとっては脅威で、危険視されたと思う。日本側からの視点とは異なる視点で日清戦争を見る必要があるし、侵攻された国にから見た日本は違ったイメージの国だ。中国にとっては琉球、沖縄はいまだに華夷秩序の中で、朝貢を行っていた属国のイメージが強いのかも知れない。
東アジアの地政学的環境も歴史的な文脈で理解すること、また、国の勢いでその解釈、理解も変動することを思い知らされた。