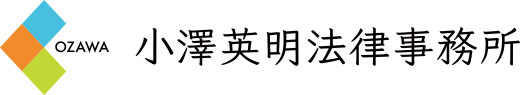コラム第33回
続・私が住んだところ(その3)
-パリ、ブローニュ・ビヤンクール(生活編)-
2025年4月21日
早 水 輝 好
ようやく今回は私が住んだところを巡る2回目のコラムの旅に戻る。アメリカでの5か月余りの研修が終わり、練馬区田柄の官舎に戻ってきてさらに1年9か月住むことになったところまでが、第29回のコラムでのお話だった。
パリへの赴任の舞台裏についてはインタビューでも少しお話ししているが、OECD(経済協力開発機構)の事務局に出向していた前任者が1992年12月に一時帰国して、後任にどうかと打診を受けたところから始まる。アメリカから帰国して9か月後のことである。アメリカに行ったとは言え、それほど海外志向がなかった私は、最初はお断りした。しかし、よくよく考えると、職員の数が少ない環境省では、「英語ができて、仕事の中身(化学物質対策)がわかる適当な年次の職員」は私しかいないのでは?と考え、人事担当者に確認したらやはりそうだという。せっかくのパリの話を捨てるのはもったいないと考え直し、面接試験にトライ、無事合格して赴任することになった。
そして第28回のコラムに書いたように、官舎の人たちに見送られ、1993年12月、家内と6歳・3歳の子供たちを連れてパリに赴任することになったのである。
ワシントンに行った時にアパート探しの大変さが身に染みたので、今回は前任者のアパートをほぼ家具ごと引き継ぐことにした。場所はパリの隣のBoulogne-Billancourt、ブローニュの森に隣接する地域である。「ブローニュ・ビランコート」と読みたくなるが、フランス語独特の読み方ルールだと「ブローニュ・ビヤンクール」となる。パリから出ている地下鉄9号線の終点「Pont de Sèvres」(セーブル橋:パリ五輪のマラソンで選手が渡った橋)からセーヌ川沿いに少し歩いたところにあるアパートで、パリ中心部にあるような古いものではなく、写真にもあるように普通の建物だった。付近には同じようなアパートが立ち並び、川沿いで地下鉄の終点だったので、私は密かに「パリの高島平」と呼んでいた。
部屋の広さは約90㎡。田柄住宅が36㎡だったから2倍以上の広さである。子供たちが喜んだのは言うまでもない。13階建ての10階の部屋で、窓からはセーヌ川(ただし遊歩道もなく砂利船が行き交うただの川)とその向こうにセーブル市の広い公園が見え、冬は荒涼とした景色だが一応見晴らしがよく、スーパー、公園、幼稚園なども近くて住みやすいところだった。床暖房で部屋が暖かかったのも良かった。
パリに到着したのは12月16日で、もうすぐ冬至の真冬。パリは日本に比べて緯度が高いので、夏は昼が長いが、冬の昼間は短い。またグリニッジとパリの経度はあまり違わないのに1時間の時差がある中央ヨーロッパ標準時を使っているので、太陽が1時間ほど遅れて移動することになり、夏は夜10時頃まで明るいが、冬は朝9時頃まで暗い。しかも西岸海洋性気候で東京のような冬晴れはなく、どんよりした曇り空の寒い日が続く。そんな暗いパリにやってきたわけで、とても「花の都パリ」という雰囲気ではなかった。秋からパリに住むと、ようやく落ち着いた頃に真冬の暗い時期になるので、1人暮らしの人などは「パリ症候群」と呼ばれる鬱病に襲われることもあるとのこと。ただ、私たちの場合は、到着したのが華やかなクリスマスの時期で、それから少しずつ明るくなってきたので、精神的に落ち込むことはなかった。
パリ赴任で心配したことが2つあった。1つはフランス語である。OECDでの仕事は英語でよかったが、生活は当然フランス語になる。幸いだったのは、大学の第二外国語で、当時「理系はドイツ語」が相場だったのに、やはり理系でもフランス語を選択した兄が使った教材が使えるし、シャンソンを聞くかもしれないから、とフランス語を選択していたことである。また、大学院の入試の時に、当時は第二外国語が入試科目にあったので、どうせみんな勉強しないだろうからここで点を稼いでやろうと少し勉強し直したこともあり、男性名詞・女性名詞があって動詞の活用も英語よりはるかに多いなど、難しい文法の基礎知識が一応残っていた。まさかそれが10年以上たってから役立つとは思わなかった。
ただ、実際にそれが使えるかどうかは話が別である。普通の買い物やレストランでの注文などは大丈夫だったのだが、複雑な話が分かるレベルではないので、市役所などでの公的な手続きの時にはいつもヒヤヒヤだった。幸い、市役所に行った時は英語ができる人を呼んできてくれたし、子供の幼稚園の見学に行った時はたまたま同時に見学した別の子のお母さんが英語ができたので通訳してくれて、事なきを得た。また、月に一度送られてくる銀行の預金の明細書で二重の引き落としがあった時は、電話で返金を求めたが先方の言うことがわからないので、課長の秘書さんに助けを求めた。「領収書を送れと言ってたのよ」と教えてもらってホッとしたことをよく覚えている。
この点では、フランス語をほんの少し勉強しただけで渡仏した家内は大した度胸だったと思う。
もう1つ心配だったのは運転免許を持っていなかったことである。前任者に確認して、仕事では不要で、子供の学校(日本人学校)もスクールバスがあるから大丈夫と言われていた。ただ、スーパーでミネラルウォーターを大量に買う必要があるので(水道水は衛生上は問題ないが、カルシウムなどが多い「硬水」なので料理にそのままは使いたくない)車が使えた方がいいし、学校の授業参観などの時も車の方が便利、ということで、一応前任者から中古車を引き継いでいた。ところが、赴任直前に日本で運転免許をとってきた家内は、日本人の同僚に同乗してもらって2~3回運転したがギブアップし、結局「あなた免許取って」ということになったのである。
早速、近所のAuto-Ecoleと呼ばれる自動車教習所に申し込んだ。フランスでは日本のような教習コースはなく、学科試験の勉強は事務所でできるが、実技の練習は路上で、教官がパリ郊外に連れ出してから車の通行量が少ない道路で練習するのである。学科試験は、フランス語での試験ではあるものの、文字と音声と動画で表示される〇×か3択の問題だったので理解しやすく一発通過だったのだが、実技試験は2回落ちてそのたびに追加教習を受けることになった。1回2時間で、最終的には100時間以上乗っただろうか。結局、3回目でようやく合格した。教習所の先生は「フランス人も3回ぐらいかかるから、こんなものよ。」と慰めてくれた。
幸い、軽い自損事故で2度ほど車を修理したものの、人身事故は起こさず運転することができた。フランスの道路で必須の縦列駐車も、バンパーはぶつけてもよいというフランスルール?のおかげでできるようになったが、ヨーロッパ特有の信号のないサークル交差点にはなかなかなじめず、パリ市内にはなるべく車で行かないようにした。遠出の旅行に車を使ったのも2回ぐらいだった。
当時のフランスの運転免許は期限がない終身免許だったが、最近は期限付きになったようで、私の免許は今も有効なのかわからない。もっとも、日本でも運転していないので、もうフランスで運転することもないだろう。
まあそんなこんなで何とか暮らしていくことができ、結果的に赴任期間が当初予定より延びて3年8か月余りブローニュに住むことになる。子供たちをめぐる話題をもう少し書きたいので、いったん閉じて、次回「子育て編」に続くことにする。
 ブローニュのアパート
ブローニュのアパート