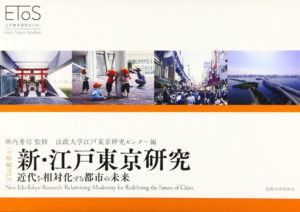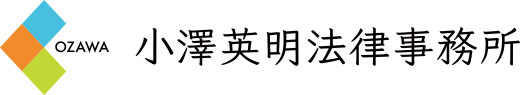都市プランナーの雑読記 その95
陣内秀信監修 法政大学江戸東京研究センター編
『新・江戸東京研究 近代を相対化する都市の未来』
法政大学出版会局,2019.03
2025年4月18日
大 村 謙二郎
2018年2月25日に開催された国際シンポジウムをベースにして、編集、加筆されて刊行されたのが本書。
法政大学に設置された江戸東京研究センターの所長(当時)をしていた陣内秀信さんがシンポジウム全体の進行、総括を行っている。陣内さんの国際人脈の広さ、深さが随所に出ているし、的確にこのシンポジウムの目的、内容を整理し、今後の研究展望を語っている。国際的な潮流の中で、いま東京に注目が集まっている所以を解き明かそうとしている。
基調講演は世界的建築家の槇文彦と人類学者で江戸下町出身の川田順造が行っている。この二人の講演は当日の話し言葉を再現する形で再録されている。
シンポジウムは3つのセッションに分かれて報告されている。
第1セッションは「江戸東京のモデルニテの姿-自然・身体・文化」と題し、我孫子信(フランス哲学、フランス思想史)をコーディネーターとしてフランス人哲学者で日本、東京の文化に詳しいチエリー・オケと日本近代史が専門のイタリア人、ローザ・カーロリが発表している。ローザ・カーロリの歩くこととWalkの違い、日本語の「歩」が意味するものから日欧の違いを論じている視点は新鮮で啓発的だった。
第2セッションは「江戸東京の巨視的コンセプト Post-Western/Non-Western」と題して、建築家北山恒をコーディネーターとしてイタリアを代表する都市計画家で非西洋世界に詳しいパオロ・チェッカレッリ、イタリア人ロレーナ・アレッシオとスペイン人ホルヘ・アルマザンが発表している。ホルヘ・アルマザンの都市論は刺激的で面白い。
第3セッションは陣内秀信がコーディネーターで「水都の再評価と再生を可能にする哲学」を主題としている。米国を代表するアーバンデザイナーで東京の都市開発にもアドバイザーとして活躍してきたリチャード・ベンダー、ミラノの運河再生に取り組んでいるイタリア人アントネッロ・ボアッティとアジア各国の水の都市を研究する高村雅彦が発表している。
江戸東京という歴史時間軸、欧米との対比、世界的な潮流としてのウォーターフロント再生の動きを論じており、参考になる。
あらためて、陣内さんのエネルギッシュな活動ぶりに感嘆の念を覚えた。
世界都市東京という語り口で夜郎自大になるのではなく、国際的な文脈の中でそれぞれの都市の魅力、特質を語り合う、このような企画とその記録はいろいろな意味で参考になるし啓発的だ。